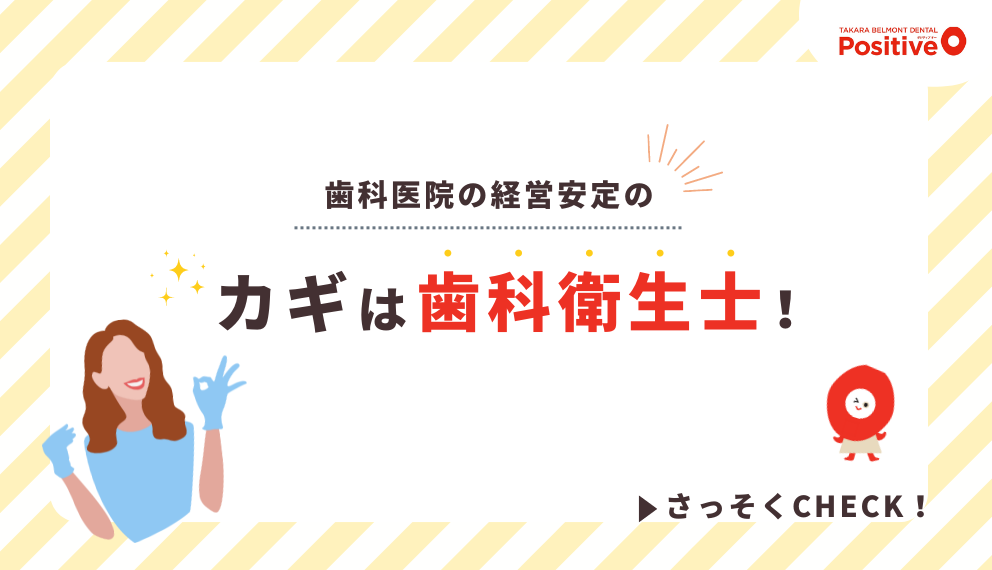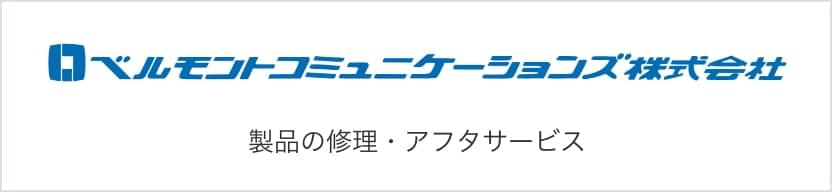コラム『税理士さんに聞く!How to 開業』第3回は『みんなが知りたい!資金調達編』です。
歯科医院開業の「資金調達」ついて、第1回の『開業前のイメージづくり編』、第2回『失敗しない物件探し編』に引き続き、数多くの歯科医院の開業を支援してこられた税理士・林哲郎先生にお話を伺います。

税理士
林哲郎先生
≪経歴≫
関西学院大学 商学部卒業
関西学院大学大学院 商学研究科修了
医療機関に特化した会計事務所での勤務を経て、平成18年4月 ネクセンチュア林会計事務所開業。
令和6年3月現在、歯科医院を中心として、約300医院の会計顧問を務め、毎年多数の歯科医院の新規開業の支援を行っている。
歯科開業のための資金調達 基礎知識
—歯科医院を開業するためには多くの資金が必要だと思うのですが、どのような資金調達先がありますか?
林先生:
1つ目に地方銀行や信用金庫、日本政策金融公庫といった銀行、2つ目にノンバンクやリース会社のような銀行以外の金融機関、3つ目に自己資金。広い視点で見ると親族から資金を借りるのも資金調達と言えますね。
—歯科開業時における自己資金の目安は1,000万円程度と聞きますが、実際にはどうでしょうか?
林先生:
銀行は、開業資金全体に対して「20%程度の自己資金を用意してください」と言ってくることが多いと思います。1億円の開業資金が必要なケースなら、自己資金に2000万円を求められることになります。2000万円を用意できる人は多くはないでしょう。
開業を考え始める30代の先生で、2000万円を貯金することって難しいことだと思います。頑張って貯金をしている先生でも1,000万円くらいじゃないでしょうか。実際には、1,000万円の自己資金でも銀行から借り入れして開業されていますよ。
—自己資金が少なくても歯科医院の開業は可能でしょうか?
林先生:
その通りで、歯科業界における開業資金は比較的調達しやすいのです。みなさんが想像しているよりも資金調達のハードルは高くありません。
自己資金が500万円の先生も開業資金の融資を受けています。なぜかと言うと、歯科医師という職業はビジネスとして経営が安定しているので、銀行は貸しても返済してもらえると考えているのでしょう。また、親が歯科医師という方も多いので、何かあれば家族からの資金援助も見込めます。
では、『自己資金500万円の先生がどうやって開業資金の融資を受けることができるのか』の一例ですが、このような先生は投資額を1億円のような高額に設定せず、ぐっと抑えた金額で開業を考えています。もちろん、物件についても無理のない範囲で選定をします。
銀行は事業計画や診療圏調査の結果など、客観的な数字で融資判断を行うので、実行可能性の高い材料を積み上げていくことが資金調達のポイントになります。あとは、先生方をサポートする私たち税理士と銀行との関係性も重要ですね。
—歯科医院が融資を受けやすい理由は何でしょうか?
林先生:
歯科医院が融資を受けやすいもう一つの理由として、倒産率の低さが挙げられます。
一般的な中小企業と比較して、歯科医院の倒産率は非常に低い水準にあります。これは、一定の患者需要や診療報酬制度による安定収益が背景にあると考えられます。この点が金融機関からみて、融資を行いやすい業種となっているのです。
また、個人の歯科医院の確定申告結果を見ても、その安定性が裏付けられます。弊社がサポートする約300件の歯科医院のうち、個人経営の歯科医院は約200件あります。その中で所得の中央値は3,000万円を超えており、1,000万円を下回るケースはわずか3%程度しかありません。一般的な事業主と比べて非常に高い水準です。

自己資金の目安と調達方法
—融資を受けやすいということですが、改めて自己資金はどの程度用意すべきでしょうか?
林先生:
先述しました通り、銀行は開業資金全体の20%程度を自己資金に求めてきます。そのため、開業資金に1億円が必要なら2,000万円、しかし2,000万円を用意できる先生は少数です。
実際に、1,000万円の自己資金で9,000万円を銀行から借り入れされている方もおられるので、開業資金全体の約10%を自己資金の最低ラインとして考える必要がありますね。また、住宅ローンを持っていれば借りにくいというのは、一部の銀行によってはあります。
ただ、住宅ローンが4~5,000万円くらいの金額なら、借入の障害にはならないケースが多いですね。
—銀行から融資を受けるためのポイントとして、保証人や不動産担保が必要だと思うのですが、その点はいかがでしょうか?
林先生:
まず、保証人については、2020年4月に民法の改正があり、保証人を取ることが難しくなりました。そのため、現在は保証人なしの融資が主流になっています。
例えば、銀行からの融資を検討している先生が、一般企業で働いている奥さんを保証人とする場合、奥さんの収入は別生計という考え方になり、公証役場で作成する「保証意思宣明公正証書」が必要になってきます。この証書の作成が非常に手間なため、保証人なしでの融資が一般的になっています。
次に、不動産担保に関しては、そもそも不動産を持っている30代の先生自体が少ないですね。実家を担保にするということが考えられるかも知れませんが、親御さんとのトラブルを考えると担保として提供しにくいと思います。銀行もトラブルになることは望んでいません。
どちらかというと、不動産を担保にした融資は少数派です。銀行は不動産で回収しても、その後の対応に困ることが多いので、あまりメリットはないですね。不動産担保の実利を銀行はしっかり見ていると思います。
—銀行は、先生方の勤務医時代の年収も融資の判断材料にするという話を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
林先生:
そうですね、最近、銀行とのやり取りの中でよく言われるのは、勤務医だった頃の年収についてですね。
経営している歯科医院が倒産した場合、勤務医に戻って給料から返済していけるのかどうかという点を銀行はみます。手取りが1,000万円以上は欲しいところです。
このところ、勤務医の給料も上がっているので、手取り1,000万円オーバーの方も多くなっています。なお、融資申し込みの際は源泉徴収票の提出を求められます。
—資金を借り入れする上で、借入期間や金利も重要なポイントですか?
林先生:
もちろんです。「借入期間と金利のどちらが重要ですか?」という質問を受けます。金利にフォーカスする方もいますが、教科書的な答えだと借入期間です。損益よりもキャッシュフローを重視すべきだと思います。
借入期間が長くなると金利の支払額は多くなりますが、毎月の返済額を抑えることができ、キャッシュフローが良い経営状態をつくりやすくなります。
ちなみに銀行によりますが、一般的には20年以内に返済を求められます。
—銀行から資金調達するポイントなどをお聞きしてきました。調達先として第一に考えるのは民間の銀行、政府系の日本政策金融公庫、どちらがよいでしょうか?
林先生:
民間の銀行ですね。日本政策金融公庫は現在、金利が2%を超えていますから。固定金利ではありますが、低くはないですよ。民間の銀行なら金利1%程度で融資を受けていることが多いです(※2024年5月 現在)。この差は大きいと思いますよ。
また、民間の銀行には積極的に医療機関の新規開業を融資しているところもあるので、税理士と相談して、ベストな資金調達先を選択してください。

無理のない合理的な範囲で資金調達を!
—融資を受けたはいいが、開業後に返済できなくなった、このような事態を避けるために資金調達をどのように進めるべきでしょうか?
林先生:
これは計画が無謀じゃないかどうか、合理性があるかという検証しかないと思います。結局、開業後の売上額がいくらになるのかは分からないので、借入額や返済額が適正かどうかは資金調達のタイミングではわかりません。
そもそも、返済できないかも?という状況になる前に行動しなければいけません。例えば、銀行と交渉して元金の返済をストップ(リスケジュール)することも検討しないといけません。
また、医院経営の中で最も高いコストである人件費についても考え直さないといけない場合があります。日本では簡単に解雇できないので、経営不振のときに解雇できるような雇用契約にしておくことも必要かも知れません。
このように状況に応じた適切な経営判断ができれば、返済できなくて破産するという事態にはならないと思いますよ。
—資金調達は開業するための資金だけでなく、開業後 数か月間の運転資金も含めておかないといけないと言われますが・・・。
林先生:
その通りです。開業規模によって変わりますが、運転資金としては1,500万円くらいを準備したいですね。銀行との交渉をしてきた経験則ですが。
ただ売上がどのように推移するか分かりませんし、いろいろな要素が絡んでくるので、1,500万円あれば大丈夫とは一概には言えません。
ちなみに歯科の倒産件数はほとんどありませんよ。47都道府県の中で最も歯科医院の多い東京都でも年間に数件ですから。
—資金調達の学びとして、銀行から融資を断られたケースがありましたら教えていただけますでしょうか?
林先生:
はい、この10年くらいで融資が受けられなかったのは1件だけでした。詳細は差し控えますがかなり特殊なケースでした。
とはいえ、私見ですが、自己資金300万円の先生でも融資を受けられるとは、みなさんには安直に思ってほしくありませんね。

資金調達の相談は早めに!
—開業準備の中で、いつ税理士に資金調達の相談をすればよいのでしょうか?
林先生:
物件が決まると、契約までが想像以上に短期間で進んでいきます。そのため、物件選びの段階で税理士に相談しておいた方がよいですね。先生自身の貯蓄状況などを検討材料に、銀行からどの程度の融資を受けれそうなのかを考え始めていきたいです。
そして、物件が大方決まってくると、お金が動き出し、本格的に資金調達が始まります。
銀行と融資について相談するときに、税理士のサポートがあれば交渉がスムーズに進むので、早めに税理士へ相談されることをお薦めします。
—最後に、開業を考えておられる先生方へのメッセージをお願いします
林先生:
我々、税理士は先生方が思い描く開業の「夢」をお金に落とし込んで、実行可能な資金計画へと発展させ、資金を調達し、開業を実現できるように全力でサポートしていきます。
一緒に「夢」に向かって進んでいきましょう。

まとめPoint
- 融資に備えて、自己資金は開業資金全体の10~20%が必要です。
- 銀行からの融資は保証人なし・不動産担保なしが主流。
- 金利の損益よりも長く借り入れキャッシュフローを重視しましょう。
- 開業資金は、開業に必要な資金だけでなく、運転資金も含めて算出します。
- 開業資金の動き出しは物件が決まるころ。だから、税理士へ早めに相談することをお薦めします。
- 資金調達をきっかけに、お金に関する知識を深めてください。